教員 × 院生対談
認知症高齢者の「意思決定支援」を切り口として、介護福祉士の実践に焦点を当てた研究に取り組む
長谷部:私は新卒から現在まで介護福祉士として現場で働いています。日々の実践でさまざまな専門性を発揮している現場の介護福祉士について、その創意工夫や努力に光を当てられるような研究をしたいと考え、大学院に進みました。
壬生:長谷部さんは学部時代から私のゼミに所属していて、もう8年ほどの付き合いになります。卒業後も連絡や相談を受けていたので、今回大学院で再び一緒に学べてうれしく思っています。長谷部さんの研究テーマである「意思決定支援」は、介護福祉士の専門性に関わる非常に重要な課題です。
長谷部:以前から実務を通して、認知症の方でも適切な支援があれば「やりたい」という気持ちを表現できることを何度も感じてきました。その経験から、認知症高齢者の意思決定支援をテーマに、介護福祉士の実践に焦点を当てた研究をしたいと思いました。先行研究が少ないため、国内外の文献を広く収集する必要があります。大学院の図書館は海外文献のデータベースも利用でき、最寄りの清瀬駅からは国立国会図書館にもアクセスしやすいので、積極的に活用しています。
壬生:介護福祉実践領域の研究はまだ浅く、これからの発展が期待されています。だからこそ、関連領域の理論研究や調査研究の方法を援用して、今後の介護福祉実践の変革・発展に資する学びを積み重ねてもらえればと思います。
長谷部:いつもゼミの時間に限らず丁寧なご指導をいただけて感謝しています。先生のご紹介のおかげで、他大学の先生方や卒業生、他の院生とも交流があり、多様な分野の実践に触れながら学びを深めています。現場での実践と研究の両立は簡単ではありませんが、利用者さんや同僚からの応援が支えになっていて、くじけそうになった時に思い出して研究に励んでいます。今後は、現在の研究テーマをさらに深めるため、博士後期課程に進みたいと考えています。
壬生:長谷部さんのように現場の実感を持ちながら研究に取り組む姿勢は、これからの介護福祉実践や介護福祉教育につながっていくはずです。未来の介護福祉実践を支える礎となるよう、さらなる活躍を期待しています。
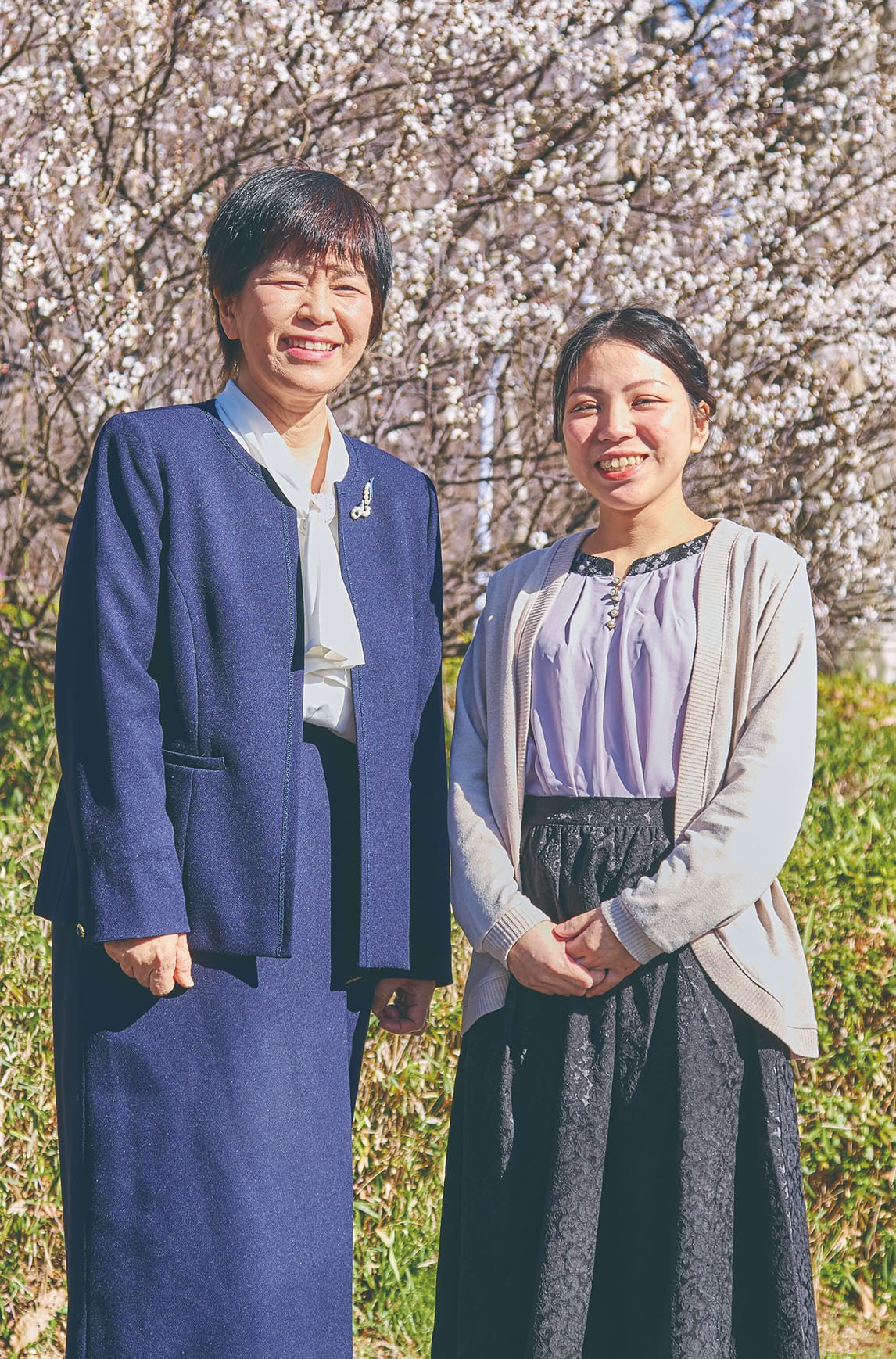
壬生 尚美特任教授(左)×長谷部 裕美さん(右)
※インタビュー内容は取材当時のものです。
