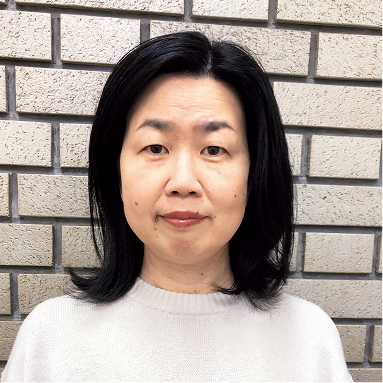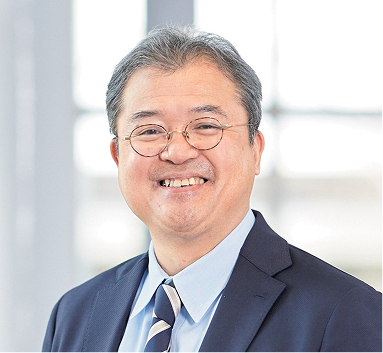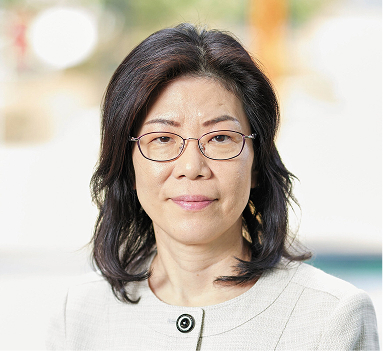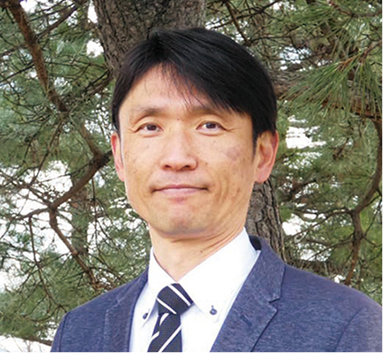クリックすると該当するコンテンツへ遷移します。
タップすると該当するコンテンツへ遷移します。
専門職大学院を知る
専門職大学院をより詳しく知る
入学希望の方向けのコンテンツを見る
お知らせ INFORMATION
専門職大学院に関する情報を掲載しています。
イベント情報 EVENT
専門職大学院に関するイベント情報を掲載しています。
専門職大学院(福祉マネジメント研究科)について NUMBERS
実践力とマネジメント力の向上を目指す人に

社会が大きく変化するなかで、私たちは社会福祉を普遍的なニーズとして認識するようになりました。しかしながら、それと同時に、生活困窮、虐待、孤立、社会的排除、貧困の連鎖など、複雑で深刻な問題を抱える人々は増え続け、自らの実践と経験だけでは解決できない状況が次から次へと生まれています。
「分野を越えて学びたい」「これまでの実践を振り返りたい」「支援のあり方を見つめ直したい」「人材育成の方法を学びたい」「福祉経営の知識を体系的に獲得したい」。専門性を深め、視野を広げること。チームや組織を理解し、他機関との連携を進めること。これらのニーズに応え、高度な福祉人材を育成することが、福祉マネジメント研究科(専門職大学院)のミッションです。
身につく力
福祉の現場経験を糧として学びなおし
実践力とマネジメント力の向上を目指します。
- ソーシャルワーク実践力の向上
- スーパービジョン
- 福祉人材の育成
- 組織と現場のマネジメント
- 実践現場の変革

数字で見る専門職大学院(福祉マネジメント研究科) NUMBERS
福祉の現場経験を糧として学びなおし、実践力とマネジメント力の向上を目指す方が入学しています。
[領域別]
※2024年度修了者

[年代別]
※2021年度〜2025年度入学者

[保有している資格]
※2025年度入学者

専門職大学院(福祉マネジメント研究科)8つの特長 FEATURES
タップすると全特長の本文が表示されます
実践力の向上を目指す
基本の再確認と最新の動向・技法を学び、対人支援専門職としての実践力の向上を目指します。
マネジメントできる力の獲得
現場のサービス向上を図り、チームや組織をマネジメントできる力の獲得を目指します。
組織のあり方等について振り返り言語化
事例研究やスーパービジョンを通して、自身や所属組織のあり方等について振り返り言語化します。
認定社会福祉士の単位を取得
多数の講義が、認定社会福祉士の大学院ルートに位置づけられています。
1年間で修士(専門職)の学位が取得
最短で1年間、現職継続者で長期履修者の場合には2年間で、修士(専門職)の学位が取得できます。
遠隔地でも仕事をしながら学べる
オンラインと対面を組みあわせたハイブリッド授業を導入し北海道や沖縄など遠隔地からの入学者も増えています。
アクセスが便利
対面授業は、清瀬キャンパスと東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分の文京キャンパスで行います。
多様な仲間との出会い
多様な仲間との交流や自由で対等な議論を通して、すぐに役立ち、生涯にわたるネットワークが築けます。
研究科長メッセージ MESSAGE

先行き不透明な時代にこそ福祉が果たす責務がある。
福祉マネジメント研究科研究科長 鶴岡 浩樹
少子高齢化、多死社会、人口減少、度重なる災害、格差拡大など、先行き不透明な、VUCAと呼ばれる現代において、福祉の重要性は益々高まっています。専門職大学院ではこのような時代の現場を支える福祉専門職、すなわち、状況を的確に見極め、柔軟に対応し、ソーシャルアクションや社会変革をもたらす専門職の養成を目指します。
クリックすると全文表示されます
本研究科は、日本で最も歴史のある福祉系専門職大学院です。20年の歳月を経て確立されたリカレント教育の手法をもとに、今日的なカリキュラム、オンライン授業の活用、時間割など仕事を続けながら学べる体制を整え、現場経験豊富な講師陣が指導にあたります。多様な専門職、さまざまな立場の方々が集い、意見を交わしながら学び合い、実践力とマネジメント力を高めていきます。
本研究科で教育の核となるのは、経験を学びに変える力で、言語化、省察、対話、批判的思考という4つの力を磨いていきます。最新理論による学びと実践への活用を繰り返して考察を深め、職場や地域に実践知をもたらし、地域共生社会の一端を担うことのできる省察的実践家を養成します。
教員×院生対談 DIALOGUE
教員と院生が学びの魅力について語ります。
専門職大学院(福祉マネジメント研究科)紹介動画 MOVIE
学びの特色や、教員・院生のインタビューを紹介しています。研究への思いを、ぜひご覧ください。
入学希望の方へ
入学を検討する皆さまへの案内を掲載しています。
※下記の「カリキュラムとキャリア」「パンフレット」「学費等」「入試情報について」をクリックすると、それぞれ適したコンテンツが表示されます。
※下記の「カリキュラムとキャリア」「パンフレット」「学費等」「入試情報について」をタップすると、それぞれ適したコンテンツが表示されます。