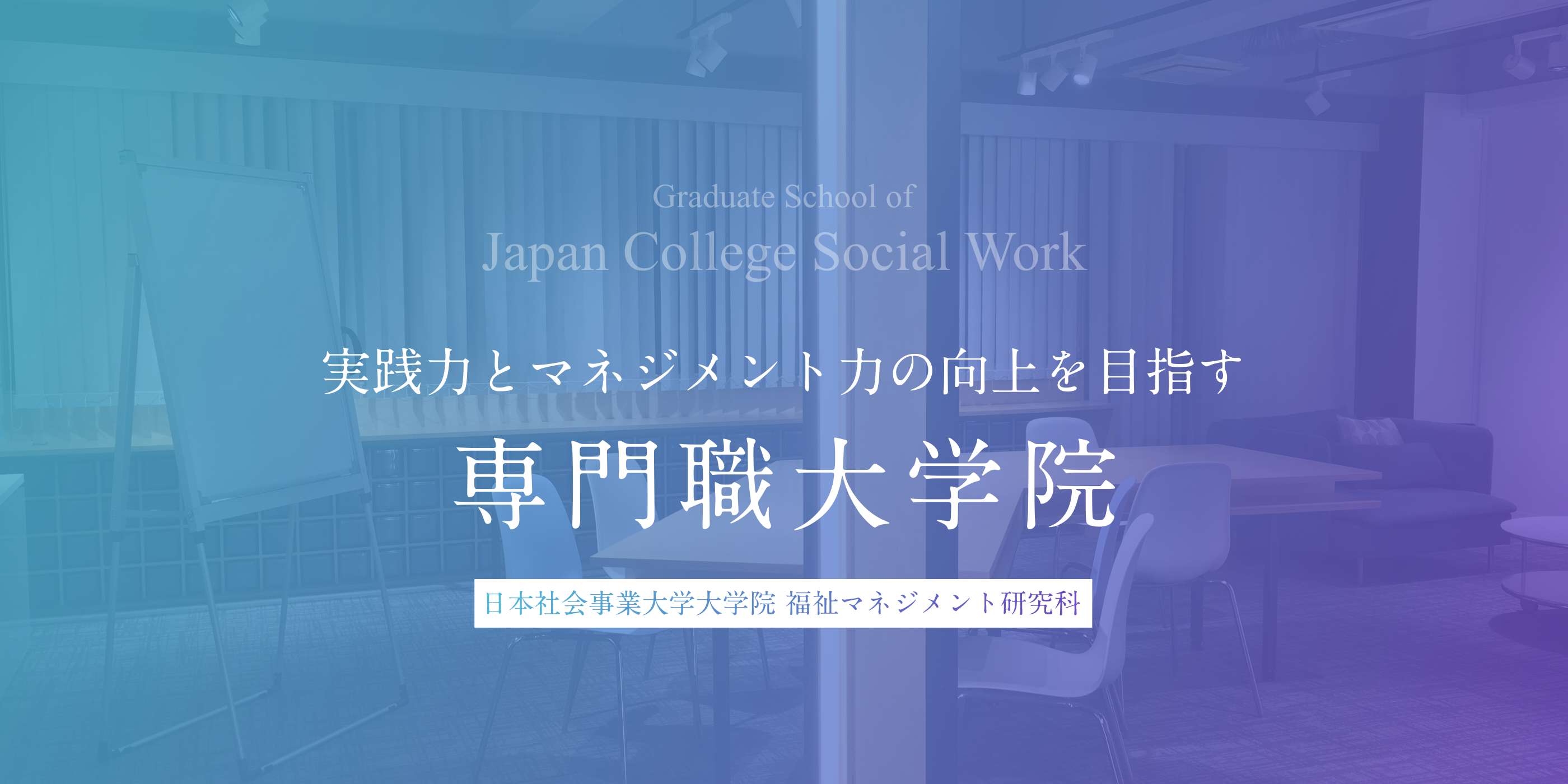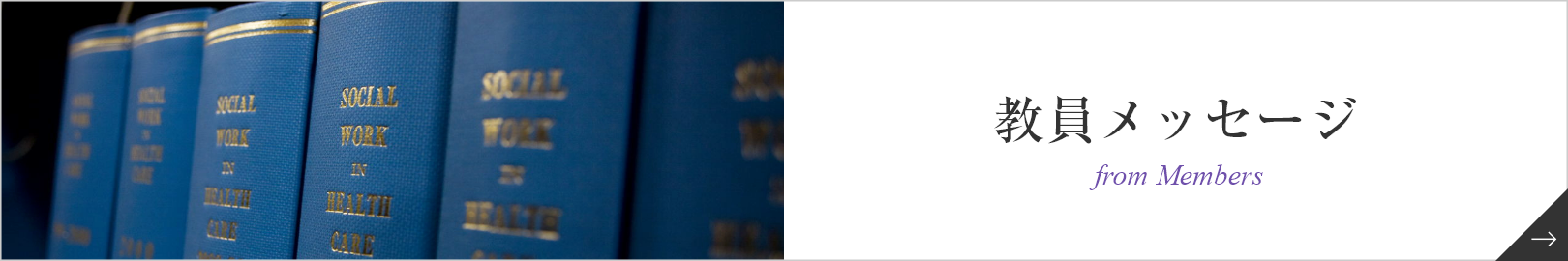イベント情報 EVENT
専門職大学院に関するイベント情報を掲載しています。
福祉マネジメント研究科
紹介動画
Movie
福祉マネジメント研究科
8つの特長
01実践力の向上を目指す
基本の再確認と最新の動向・技法を学び、対人支援専門職としての実践力の向上を目指します。
02マネジメントできる力の獲得
現場のサービス向上を図り、チームや組織をマネジメントできる力の獲得を目指します。
03組織のあり方等について振り返り言語化
事例研究やスーパービジョンを通して、自身や所属組織のあり方等について振り返り言語化します。
04認定社会福祉士の単位を取得
多数の講義が、認定社会福祉士の大学院ルートに位置づけられています。
051年間で修士(専門職)の学位を取得
最短で1年間、現職継続者で長期履修者の場合には2年間で、修士(専門職)の学位が取得できます。
06遠隔地でも仕事をしながら学べる
オンラインと対面を組みあわせたハイブリッド授業を導入し北海道や沖縄など遠隔地からの入学者も増えています。
07アクセスが便利
対面授業は、清瀬キャンパス(西武池袋線「清瀬」駅からバス6分)と文京キャンパス(東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分)で行います。
08多様な仲間との出会い
多様な仲間との交流や自由で対等な議論を通して、すぐに役立ち、生涯にわたるネットワークが築けます。