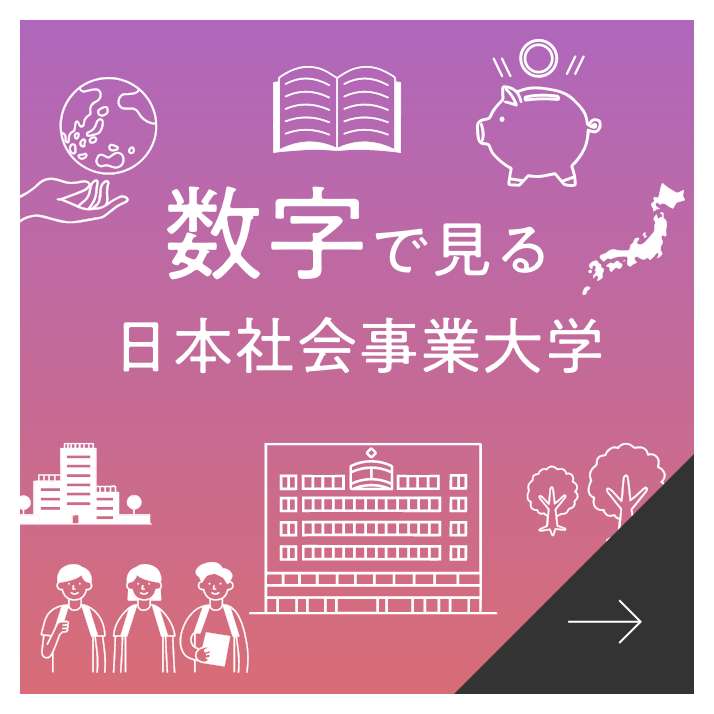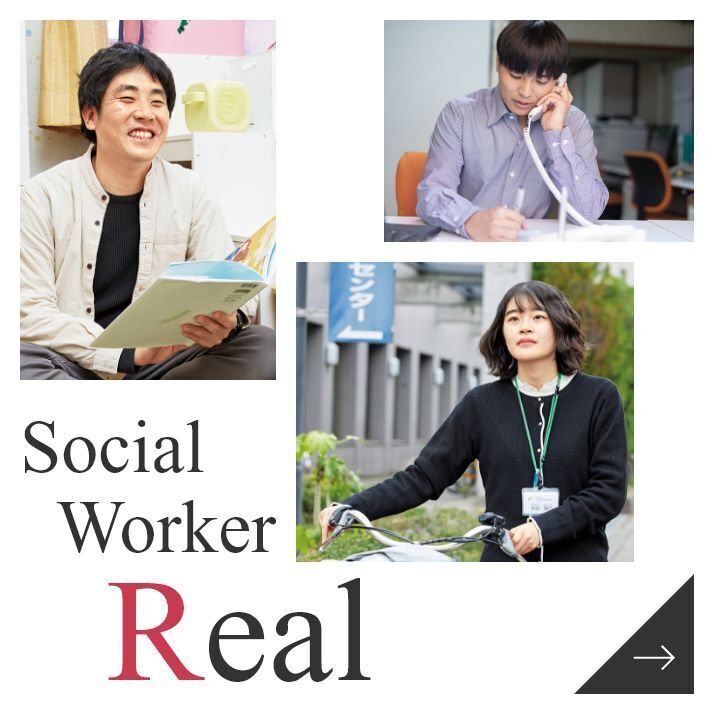多心型福祉連携センター
多心型福祉連携(多種多様な主体が対等の立場で自発的に連携し協力・補完し合いながら地域社会が抱える福祉問題を解決しようとする取り組み:Polycentric Partnership in Community Welfare)のあり方を研究する。
「社大の農的空間創出(新農福連携)プロジェクト」の活動状況について
農林水産省「令和6年度農山漁村振興交付金(都市農業機能発揮対策(都市農業共生推進等地域支援事業))都市農地創設支援型」に採択され、2024年7月より「社大の農的空間創出(新農福連携)プロジェクト」を実施しています。
キャンパス内でジャガイモ、サツマイモ、のらぼう菜等を栽培し、雑草を除草するためにヤギ(2024年4月生まれの姉妹2匹)を飼育しています。そのヤギを見るために、近隣にある複数の保育園の園児たちが毎日のように訪れます。2匹のヤギを介した、学生×学生、学生×教職員、教職員×来校者...緩やかな交流が始まっています。
オープンキャンパス(7月21日)では、社会福祉学部の永嶋准教授が「農的活動による世代間交流と福祉」というテーマで講義をしました。参加者は、実際にヤギとふれあいながら、「農」を通した社会の課題を考えました。
夏休み後は、本事業で連携している保育園のご厚意によりポニー2頭に来てもらい、グランド横の雑草を食べるポニーと園児・学生たちとの交流企画(10月22日)を行いました。
また、社大祭(10月26~27日)では「ヤギの散歩」が大人気でした。こどもも大人も餌(ニンジン)やり体験を楽しみました。そして、学内で名前を募集し、100件を超える候補から投票により「おこめ」「おこげ」に決まりました。「おこめ」と「おこげ」の存在が、笑顔の循環をつくっています。
11月には、社大で収穫したサツマイモを使い、地域の老人クラブの皆様のご協力も得て、近隣の保育園で焼き芋会が行われました。農的な活動を通して、このような園児・大学生・高齢者による多世代交流の場が実現しています。

ヤギ来学(左おこげ、右おこめ)

ヤギ学内散歩

落ち葉堆肥コンポスト設置準備

落ち葉堆肥コンポスト設置準備

ポニーとの交流

ポニーとの交流

サツマイモ収穫

サツマイモ収穫

焼き芋会

焼き芋会
学長室多心型福祉連携センターの本間律子学外研究員の受賞について
2024年9月28日(土)、学長室多心型福祉連携センターの本間律子学外研究員が、第19回片岡好亀賞を受賞しました。同賞は、社会福祉法人名古屋ライトハウス創立者の一人である片岡好亀氏を記念して、同法人の60周年に際して設立された賞です。さらに、11月22日(金)には、埼玉県より本間研究員の長年の研究および社会的な貢献が認められ、第18回塙保己一賞大賞を受賞しました。当センターでは、本間研究員の受賞に心からの祝意を示すとともに、今後とも外部の有為な研究者等と様々な形での連携を進めてまいります。
農林水産省「令和6年度農山漁村振興交付金(都市農業機能発揮対策(都市農業共生推進等地域支援事業))都市農地創設支援型」に採択されました
農林水産省の「令和6年度農山漁村振興交付金(都市農業機能発揮対策(都市農業共生推進等地域支援事業))都市農地創設支援型」に、本学が提案・応募した「市民に開かれたキャンパス内の農的空間を活用した地域の振興」が、「宅地等の空閑地を活用した農的空間の創出を支援する取組」として採択されました。
多心型福祉連携の一形態として、広い意味での農福連携のあり方を検討し、多世代交流を視点とした農的活動により地域のさまざまな資源の共生を推進する研究を行います
2024年7月よりこれを「社大の農的空間創出(新農福連携)プロジェクト」と名付け、すでにキャンパス内において、保育園と老人クラブとの交流活動や、ヤギを飼育することによる人と人とのインタラクションの検証等を実施しているところです。

ジャガイモの収穫

ジャガイモの収穫

ヤギと園児

中庭でのヤギの様子

サツマイモの植え付け

サツマイモの植え付け
3年連続で「災害」をキーワードに社大福祉フォーラム自主企画シンポジウムを行いました。
社大福祉フォーラム2025
自主企画分科会2 シンポジウム「災害における認知症の人と介護家族への包括的支援について~能登半島地震における支援から考える~」
日時:2025年6月22日(日)10:00~12:00 会場:A202教室
ご挨拶
入部寛先生(社会福祉学部教授/多心型福祉連携センター長)
企画趣旨
下垣光先生(社会福祉学部教授)
話題提供
「令和6年能登半島地震 金沢医科大学からの報告 ~災害時、災害後の認知症の人の生活を支えるために今できること~」
橋本玲子先生(金沢医科大学精神神経科学助教)
「能登半島地震から考える認知症の人と家族の災害時支援の課題」
北川進先生(専門職大学院講師)
令和6年能登半島地震に際し災害派遣精神医療チーム(DPAT)で出動された、金沢医科大学の橋本先生をお招きしました。橋本先生からは、避難所(1次避難所、1.5次避難所、2次避難所)で認知症の人とその家族が直面する環境変化による負担等についてご報告いただきました。次に、災害ソーシャルワークをご専門とされている北川先生には、災害からの学びを包括的支援体制の取り組みに反映させていく視点についてご報告いただきました。最後に、下垣先生より、認知症の人が大切にしていること、どこに住みたいのか、誰に声をかけてもらいたいのか等、日頃から把握するかかわりの大切さについてお話しいただきました。フロアの皆様からもご質問やご感想をいただき、活発な意見交換の場となりました。

下垣先生による趣旨説明

発表される橋本先生(金沢医大)と北川先生

会場(A202教室)の様子
社大福祉フォーラム2024
自主企画分科会3 シンポジウム 「環境・災害と福祉の予防的支援」
日時:2024年6月22日(土)13:30~15:00 会場:A401教室
解題
「環境、災害と福祉の予防的支援」 入部寛先生(社会福祉学部教授/多心型福祉連携センター長)
報告
「環境・災害と福祉の予防的支援」 木戸宜子先生(専門職大学院教授/通信教育科長)
「在宅医療と予防的支援 ~コロナ?災害?平時からの備え」 鶴岡優子氏(在宅療養支援診療所 つるかめ診療所所長)
「子ども家庭福祉領域における予防的支援」 須江泰子先生(専門職大学院講師)
「環境・災害と福祉の予防的支援」 大島隆代氏 (文教大学人間科学部准教授)
フロアとの意見交換
予防的支援を研究テーマにされている木戸先生を中心に、在宅医療のお立場から鶴岡先生、児童相談所のご経験から須江先生、災害時支援に関するご研究から大島先生にシンポジストをご依頼しました。先生方のご発表のあと、フロアから高橋先生や曽根先生、同窓生の皆様からコメントをいただき、意見交換が深まりました。多心型福祉連携センターで準備した、コーヒーと三角柱名札(学長室オリジナル)も好評でした。シンポジウムの内容は社会事業研究第64号に投稿しました。

当日の打合せ(研202教室)のあとで、記念撮影

予防的支援について発表される木戸先生

前多心型福祉連携センター長の高橋先生よりコメントをいただきました
社大福祉フォーラム2023
自主企画シンポジウム 「災害と福祉の支援と受援」
日時:2023年6月24日(土)13:30~15:30 会場:A401教室・オンライン
はじめに
高橋幸生先生(社会福祉学部教授/学長室 多心型福祉連携センター長)
研究報告
「済生会における災害対応の現状と課題」 原田奈津子氏(社会福祉法人 恩賜財団 済生会 済生会保健・医療・福祉総合研究所 上席研究員)
実践報告
有坂幹朗氏(社会福祉法人 浴風会 地域サービス部長)
今井遊子氏(社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策企画部 副部長/災害福祉支援活動推進室長)
指定発言
藤野将睦氏(ビーサイドユー株式会社 代表取締役社長)
総括
潮谷有二氏(社会福祉法人 慈愛園 慈愛老人ホーム・ケアハウス 施設長)
日本社会事業大学と縁が深く、日本の社会福祉をリードする団体の皆様にお集まりいただきました。シンポジストの皆様には、「災害と福祉の支援と受援」の観点から活動をご紹介いただき、意見交換を行うことによって、それぞれの取り組みの視点を整理しました。そして、ご来場いただいた潮谷先生、北川先生からコメントをいただきました。シンポジウムの内容は、社会事業研究第63号に投稿しました。

シンポジスト(左より原田様、有坂様、今井様)の皆様

本学前理事長の潮谷義子先生(済生会 会長)にコメントいただきました

元社会福祉研修センター長の潮谷有二先生(慈愛園)による総括