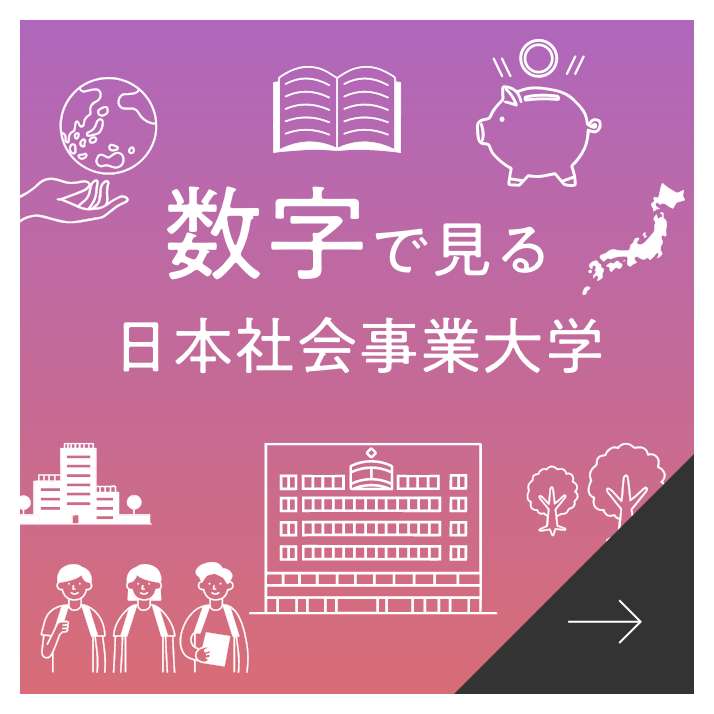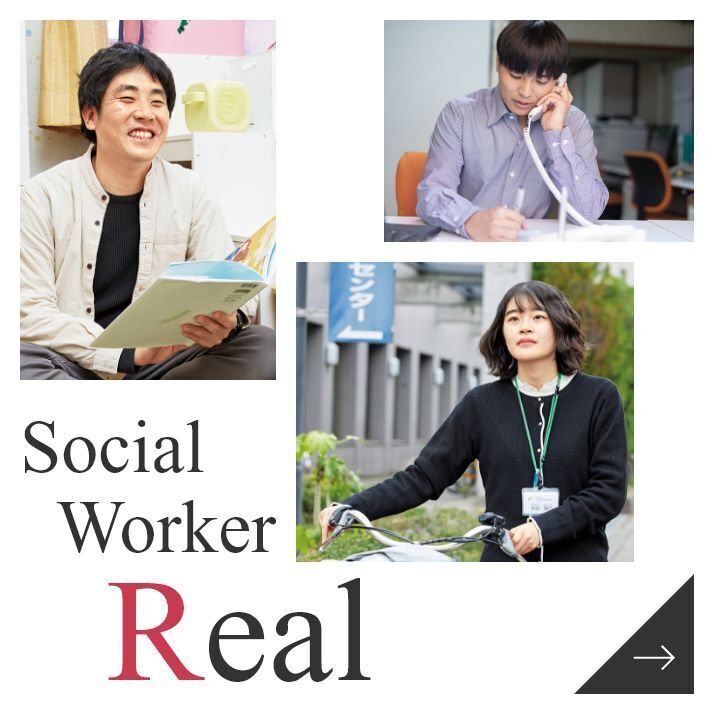10よりよい福祉サービスを目指すために
欠かせない「プログラム評価」とは?

解に挑む研究者
新藤 健太准教授
社会福祉学部 福祉援助学科
- Profile
- 日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科准教授。日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程修了(社会福祉学博士)。国立障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科、茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科、群馬医療福祉大学社会福祉学部等を経て、2022年に日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科に講師として着任。2025年より現職。専門分野はソーシャルワークとプログラム開発・評価。
近年、さまざまな福祉制度の整備が進んでいますが、そのすべてが効果的で価値があるかどうかは、客観的に評価しなければわかりません。支援を受ける人々の自立を支える効果的な福祉サービスを開発するためには、どのようなプロセスが必要なのでしょうか。公的事業などを客観的に評価する「プログラム評価」について研究する新藤准教授の取り組みを紹介します。
#EBP#科学的根拠に基づく実践#プログラム評価#社会的インパクト評価
SDGsアクション








客観的な評価方法に基づき、
効果的な福祉サービスを開発する
私は「ソーシャルワークとプログラム評価」を主な研究テーマとしてきました。
社会福祉の分野では、さまざまな人々の困りごとを解決するために多くの取り組み(プログラム)が行われています。しかし、その取り組みが実際に期待した成果を出せているのかどうかを明らかにするのは簡単ではありません。そこで重要になるのが「プログラム評価」です。
これは、「本当に必要とされているのか(ニーズ評価)」「なぜ効果があると考えられるのか(セオリー評価)」「計画通りに進んでいるか(プロセス評価)」「どのような結果や影響が出ているか(アウトカム・インパクト評価)」「費用対効果の観点から妥当な内容か(効率性評価)」といった観点から対象のプログラムを評価する方法です。プログラムのもつ価値や効果を客観的に示し、改善すべき課題を明らかにします。

これまでに、障がい者の就労移行支援、生活困窮者の就労支援、障がい者の芸術文化活動促進支援、一人親家庭への食糧配布支援といったプログラムの検討に、この方法論を用いてきました。さまざまなプログラムの価値を明らかにするとともに、社会に向けて発信し、より効果的なものへと改善できるよう努めています。
施設から地域へ。
自分らしく暮らすための「移行」を支援
こうした研究のなかで、力を入れてきたもののひとつが「知的障がい者の地域生活移行支援」についてです。
日本では長年、多くの知的障がいのある方々が入所施設で生活してきました。しかし、時代が進むにつれ、障がいの有無にかかわらず、地域の中で自分らしく暮らせる社会づくりが進められるようになりました。とはいえ、施設から地域生活への移行にはさまざまな課題があります。

たとえば、地域で自分らしい生活を実現するには、住まいの選択肢や日中活動の機会を増やすなど、さまざまな環境の整備が必要です。しかし、現状では、支援付の住まいであるグループホームなども数が足りておらず、日中に参加できる活動や仕事の場も十分に整備されているとは言えません。また、長年施設生活してきた人々の高齢化が進み、家族もまた高齢化するなかで、支援機関や地域住民の助け合いなど、従来の支え方を見直す必要もあります。さらには、地域住民の障がいに対する理解や障がいのある方々とのかかわり方も問われています。このように、誰もが地域の一員として暮らせる社会にするにあたり、解決しなければならない問題が山積みです。
そこで私たちは、実際に地域移行にたずさわっている現場の方々と協力しながら、より効果的な支援の方法について研究を重ねました。
最初に行ったのは、地域移行に必要となる様々な人たちの変化を明らかにすることです。具体的には、本人や家族、地域社会、そして支援者が、実現に向けてどう変わるべきかを整理しました。
次に上記の内容をふまえて、本人や家族に働きかけることに加え、支援者自身の力を高め、地域の方々とも協力し合う方法を具体化。実用的なプログラムモデルの開発に取り組みました。
さらには、このプログラムモデルが取り組みの効果に関連しそうかを全国的に調査。その結果、モデルに近い実践を行っている施設ほど、地域移行に関係する実績も高いことが明らかになりました。モデルづくりの過程で、十数年にわたる取り組みの結果、地元に帰り、地域移行を果たした知的障がいのある方のエピソードをお聞きしたことも、強く印象に残っています。
社会福祉にかかわる者として
SDGsの達成に貢献したい
今後は、ソーシャルワークの実践と研究が密につながり、互いに機能し合うような仕組みづくりにも取り組みたいと考えています。
私が福祉現場で働いていた当時は、実践経験や個人の感覚が重要視される傾向にありました。これらは現場における貴重な財産ですが、加えて理論やエビデンスに基づいた支援を取り入れることも大切だと考えます。医療など他の専門領域がそうであるように、社会福祉においても当たり前にそうした動きを取り入れることで、さらに質の高い支援が可能になると思っています。よりよい環境づくりのために、引き続き現場の方々とともに、活用しやすいプログラム開発・評価の方法を探っていきます。
私が研究の先に描くのは、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念が地域や国境を越えた共通の価値として広がる社会です。
SDGsの17の目標(ゴール)には、さまざまな格差を埋め、誰もが健康であり、平等に教育を受けられるようにするといった、世界中の人々が共通して大切にすべきテーマが含まれています。私自身も、社会福祉の分野に身をおき、ソーシャルワークの実践や研究に取り組む立場として、目標達成に貢献したいと考えています。
理論やエビデンスに基づいた支援で、自分らしく生きようとするすべての人々をごく当たり前にしっかりと支えられる。適切なタイミングで必要な支援を求めることができ、それが社会のなかで当然のこととして受け入れられる。そんな風に、誰もが尊重される社会の実現に向けて、研究を続けていきます。
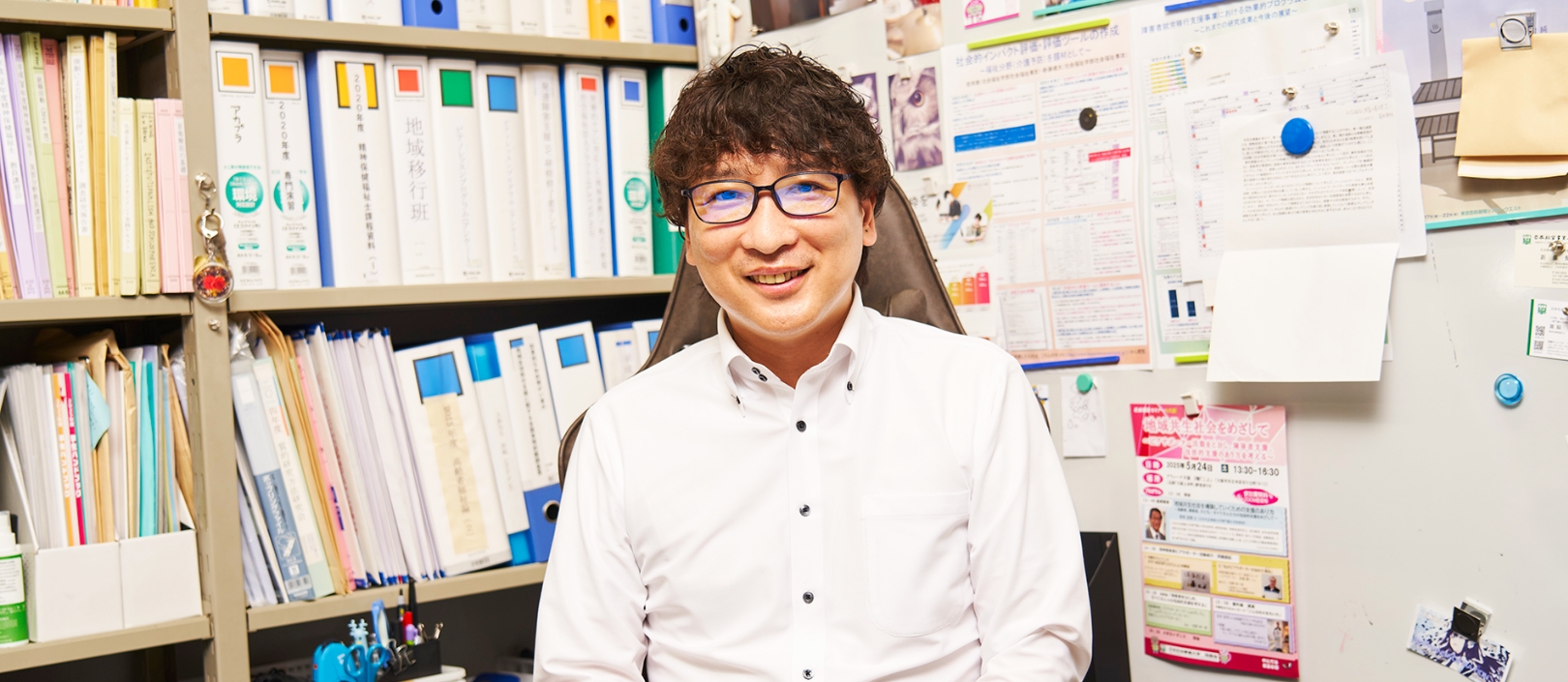

私は社会福祉を「社会の努力」ととらえています。ソーシャルワークの価値観においては、「自立」は「一人で何でもできること」を意味しません。人は皆、時に誰かの手を借り、困難や失敗を経験しながらも自分らしく生きていこうとします。その姿勢こそが大切で、価値あるものと考えます。しかし、自助努力には限界があります。そこで人々を支えるための「社会の努力」としてあるのが「社会福祉」なのです。社会福祉は、「生活」というその人だけの領域に専門性をもってかかわることができる魅力的な分野。誰かの生活をそばで支え、助けになりたいと考えている方はぜひ、日本社会事業大学で一緒に学びましょう。皆さんとともに、社会福祉に貢献できる日を心から楽しみにしています。