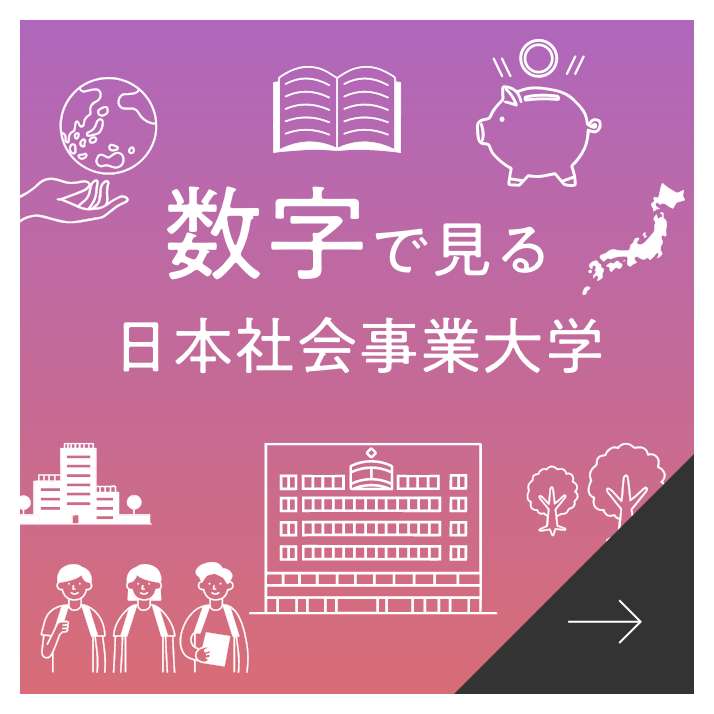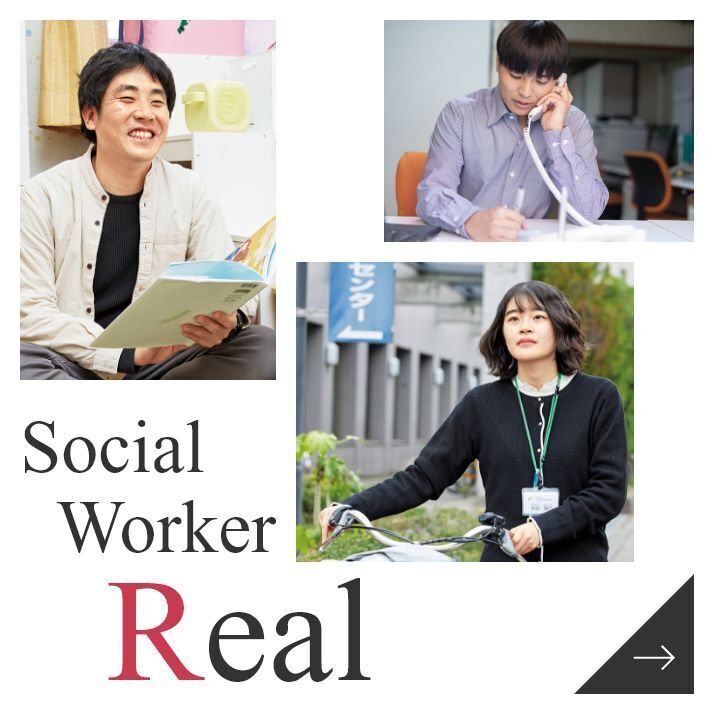07障がい当事者の声を正しく社会に届ける制度をつくるには?

解に挑む研究者
二神 麗子講師
社会福祉学部 福祉援助学科
- Profile
- 2014年日本社会事業大学社会福祉学部福祉計画学科卒業。群馬大学大学院教育学研究科修士課程修了、立命館大学大学院先端総合学術研究科先端総合学術専攻博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。群馬大学教育・学生支援機構学生支援センター産学官連携研究員の後、助教、同大学教育学部助教等を経て2023年4月より現職。主な研究テーマは障害者福祉(特に聴覚障害)、福祉政策、特別支援教育他。
近年、障がい当事者の意見を取り入れた政策や法律が施行されるようになってきました。一方で、なかには本来当事者たちが法制度に求めていた内容が必ずしも反映されているとは言えない例もあります。こうした問題を解決するべく研究を続ける、二神先生の取り組みをご紹介します。
#障がい者福祉#福祉政策#特別支援教育#聴覚障害
SDGsアクション



実情に沿った法制度を目指し
政策決定プロセスをひもとく
私はこれまでに手話に関する条例が定められるプロセスに着目し、そこに当事者の意見がどのように反映されるのかを明らかにしていく、という研究に取り組んできました。福祉政策の分野になるでしょうか。
近年、福祉に関する法律や政策を立案・実行する際には「障がい当事者の声を生かす」ことが重要視されています。一方で、当事者の話によると「思っていたものと違った」「本来求めていた制度とは異なる」などギャップを感じるケースもめずらしくないようです。
私の研究では、こうした問題がなぜ起こるのか、当事者の声がどのようにして政策に反映されるのか、あるいはされないのかを、「手話言語条例」の「意思決定プロセス」に注目してひもといていきます。

代表的なケースとして取り上げたのは、群馬県と前橋市の「手話言語条例」です。これは、手話を言語として認め、その普及や教育を後押しするための条例です。なぜこのような条例が必要なのか。手話や聴覚がい者がさらされてきた差別や偏見の様子や、条例にかける願いを、聴覚障がいのある当事者から、手話を通じて聞き取りました。また、条例が議会で通されるまでにどのような議論や関係者間の調整があったのかを内部に入り込んで調査しました。こうした条例制定プロセスをくわしく解明することで、当事者の声がどのような形で政策に反映されていくのか、手がかりを得られると考えています。
学生時代に得た気づきが
研究の道しるべに
この研究を始めたきっかけは、大学時代にさかのぼります。当時、私は障がいのある学生を支援する活動にたずさわっていました。大学側の組織的なサポート体制は整っておらず、学生の自主性に支えられた取り組みが中心で、当事者だけでなく私たち支援する側も負担を感じ、心身ともに疲れきっている状況でした。
そこで視覚障がいのある友人たちと協力し、大学に対して体制の改善を求めた「意見書」を作成したこともあります。しかし、なにか状況が改善することもなく、落胆したのを覚えています。
やがて気づいたのが、こうした問題は教育機関に限った話ではないということでした。国の法律や政策の提言にかかわった障がい当事者らからは、「私たちの声が十分に反映されていない」「法案が骨抜きにされてしまった」という声が発信されていました。

「せっかく当事者の参加がかなったのに、なぜ、障がい当事者の願いが政策に反映されないのだろうか」と怒りに似た疑問を、そのときに抱きました。
転機が訪れたのは、大学院に進んでからです。恩師の紹介で群馬県と前橋市の「手話言語条例」制定にたずさわる機会に恵まれたのです。政策決定の舞台裏を見て、さまざまな人々が絶妙な力関係のもとに意思決定していく様を見ました。
こうした「仕組み」を解き明かすことで、社会の課題を解決するためのメカニズムを一つでも明らかにできるのではないかと思い、研究を続けています。
「当事者の声」が
法制度に与える影響を明らかにする
現在、日本では600以上もの自治体で「手話言語条例」が施行されています。2025年6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が制定されました。これはろう者(手話を母語とする者)にとって、大きな一歩となる出来事です。
しかし、課題があるのも事実です。表面的に法律の条文だけを評価するのでなく、それが国政の内部でどのような議論や意思決定プロセスの先に成立したのかを明らかにしなければ、本当の意味での、障がい者による当事者参加は実現されないと思っています。
手話施策推進法が今後どのような形で社会に根づき、改善されていくのか、慎重に行く末を見守っていくつもりです。
よく、恩師がおっしゃっていた言葉があります。
「われわれの時代に起こった出来事をきちんと記録して、後世に残していくことが学問にとってとても大切」。これは私の研究スタイルである「とにかく足を動かして、人と直接会うこと」とも通じています。
条文にたった一文字を加えるだけでも、たくさんの人が思いや時間をかけて議論した末に、つくり上げられています。しかし、そうした作業の大部分は記録として後世に残りませんし、証人がいつまでも生きているわけではありません。一連の研究にご協力いただいた方で、すでに亡くなられた方もいます。あのとき、「思い」を直接聞くことができて本当によかった、と感じます。


目に見えるものだけがすべてではありません。大切なのは物事の背景について考える姿勢です。いま身近で起きている問題を、国や政治家、社会のせいだと批判することは簡単です。しかし、裏では何が起こっているのか、なぜそうなっているのかをじっくりと考え、さまざまな角度から分析してみましょう。その経験があれば、世の中の理不尽さに直面しても、柔軟に対応できるソーシャルワーカーになれると思います。