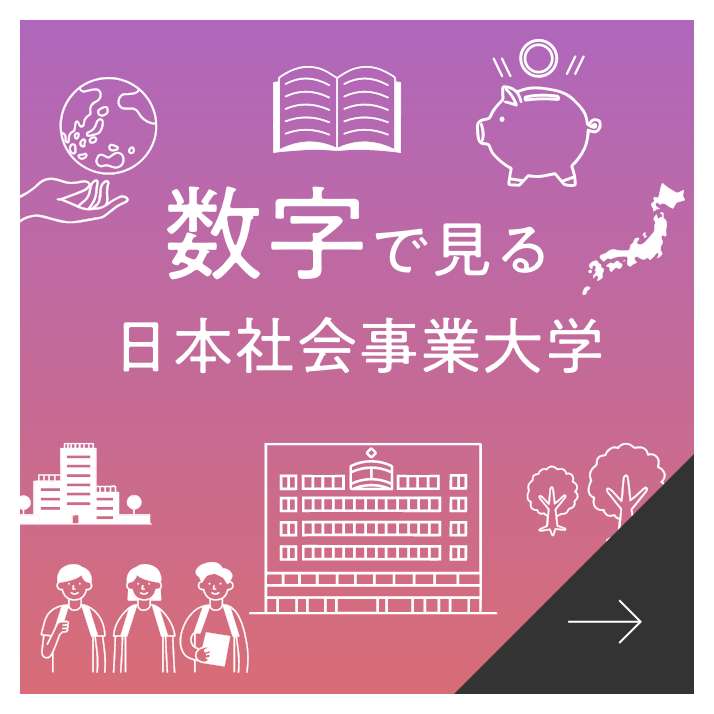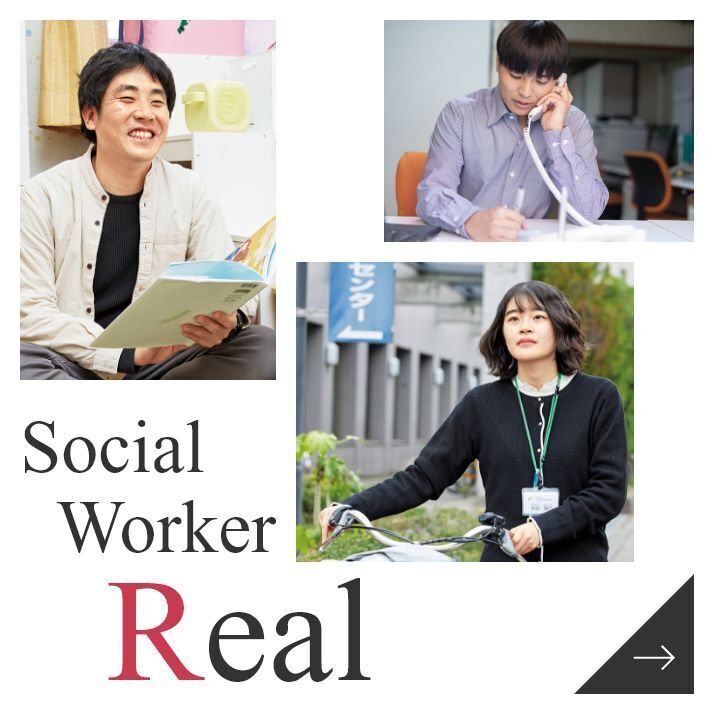08制度の枠組みからこぼれた人びとに寄り添い
地域の力を高める支援とは?

解に挑む研究者
菱沼 幹男教授
社会福祉学部 福祉計画学科
- Profile
- 日本社会事業大学社会福祉学部福祉計画学科教授。1994年日本社会事業大学卒業。同年、狭山市社会福祉協議会入職。退職後の1998年に日本社会事業大学大学院博士前期課程入学、2001年同修了。在学中はNPO法人地域福祉研究所等に勤務。修了後は教育機関等に勤めながら、日本社会事業大学博士後期課程へ進学。2010年博士(社会福祉学)取得。同年、日本社会事業大学に教員として赴任。2022年から教授。多数の自治体、各社会福祉協議会の要職も務める。専門は地域福祉、コミュニティソーシャルワーク等。
福祉制度が整いつつある現代においても、地域社会にはさまざな生きづらさを抱えている人びとがいます。制度の枠組みからこぼれた人びとに寄り添い、誰もが暮らしやすい地域社会を実現するために何が必要なのでしょうか。その方法について「地域福祉」を専門とする菱沼教授にお話を伺いました。
#コミュニティソーシャルワーク#コミュニティワーク#地域支援
SDGsアクション









一人ひとりに向き合い、
その人びとが暮らす地域にも
目を向ける
長年にわたり、一人ひとりの生きづらさに向き合いながら、地域の力が高まるよう支援していくコミュニティソーシャルワークについて研究してきました。
地域には、子ども食堂や高齢者サロンのように、人びとが集う居場所があります。自分の気持ちを安心して語れる仲間と共に過ごせる場所は、孤独や孤立をなくしていくうえで大切なものであり、こうした地域活動を支えることを「地域支援」と言います。
しかし、地域の居場所は、そこに行ける人にとっては大事な場所になりますが、行けない人たちもいます。孤独や孤立は、そこに行けない人ほど感じやすいものであり、居場所活動としての「地域支援」だけでなく、そこにつながらない一人ひとりに対する「個別支援」も大切になります。

この個別支援と地域支援を結びつけていくのがコミュニティソーシャルワークです。
地域支援の重要性を
広く自治体に呼びかける
日本の地域生活支援における個別支援と地域支援の状況を把握するため、2008年と2019年に全国調査を実施しました。10年経年調査の結果、個別支援は充実してきているものの、地域支援はいまだに十分でないことが明らかになりました。
なぜ地域支援が重要なのか。それは孤独や孤立、差別や排除という問題は地域社会から生まれるものだからです。これらの問題は、人びとが社会に参加する上での壁となり、彼らの生活にも大きな影響を及ぼします。
全国調査の結果をもとに、地域支援を行う人材配置が有効であることを示し、このデータを参考にコミュニティソーシャルワーカーの増員を行った地域もあります。

さらに、地域支援を推進する方策を明らかにするため、2つの市を対象に、地域支援者がかかえる問題とその解消方法について調査分析を行いました。その結果、地域支援においては、自治会や民生委員といった地域の方々との関係構築や、職場内外の地域支援者との連携が有効だとわかったのです。
現在、地域福祉実践者を対象とした研修を各地で行っており、こうしたデータに基づいて、地域支援者が担当する範囲の適切な規模や、地域内の多様な人びとの声を聴く重要性を伝えています。
また、課題解決に役立つツールの開発もしています。その一つである「9マスシート」は、個別支援と地域支援を一体的に検討できるものであり、全国各地で活用されています。これからも実践現場の方々の力になれる研究を進めていきたいと思っています。
人びとの幸せを願う心を
次の世代へとつなげていく
福祉の現場を取り巻く状況は日々変わります。そのため、研究・教育に終わりはなく、常に自分自身をブラッシュアップしていかねばなりません。
今後の目標は、日本の社会福祉実践において未成熟な地域支援を高めていくことです。現在、いくつかの地域で多様な人びとが合流できるプラットフォームづくりに関わっており、そうした実践から見いだされてきた知見をもとに「支持的地域支援」など新たなアプローチの理論化に取り組んでいます。
また、「グリーフケア」にも注目しています。グリーフとは、愛する人との死別や離別など、さまざまな喪失によってもたらされる哀しみなどの感情です。既存の居場所の多くは、楽しく過ごすことが中心になっており、深い悲しみをかかえる人びとにとっては行きづらい場合があります。こうした気持ちを安心して語れる地域づくりに貢献できたらと思っています。
日本社会事業大学では新学科の名称に「共生社会デザイン」という言葉を用いています。その名が示す通り、人とつながりたいときにつながることができ、孤独や孤立、差別や排除のない社会をみんなで創っていきたいという想いが込められています。


社会福祉は、自分が向き合う相手はもちろん、自分の幸せにもつながる仕事です。しかし、支援をするにあたり、忘れてはならないことがあります。それは「相手の気持ちを完全に理解することはできない」ということ。これを見失うと、ひとりよがりな支援になってしまい、相手を支援したいという自分の気持ちを満たそうとするだけの支援者になってしまいかねません。「必要以上の支援は相手の力を奪う」ということを肝に銘じて、常に相手を理解しようとする姿勢を忘れずに「本当に必要な支援とは何か」を考える力こそが社会福祉の専門職には必要です。日本社会事業大学での学びや出会いは、そうした力をはぐくむ土台になるでしょう。