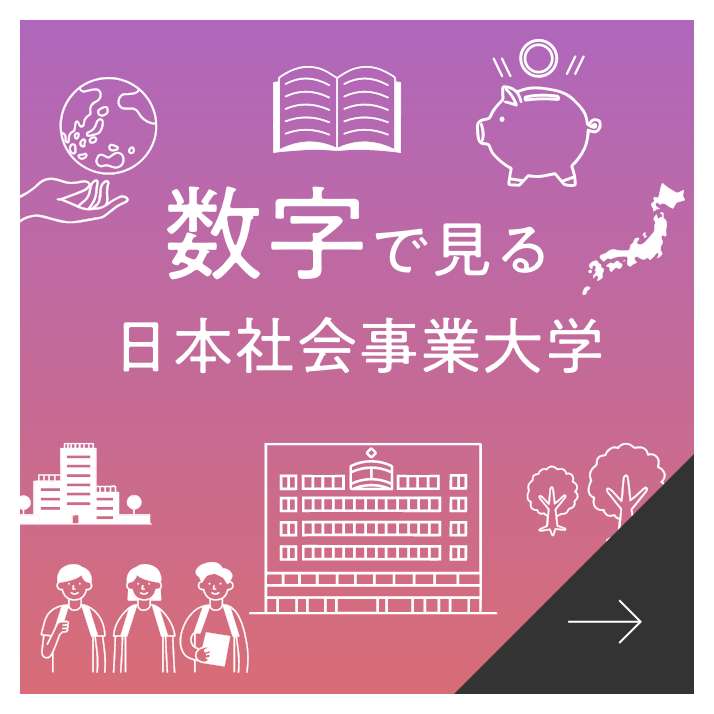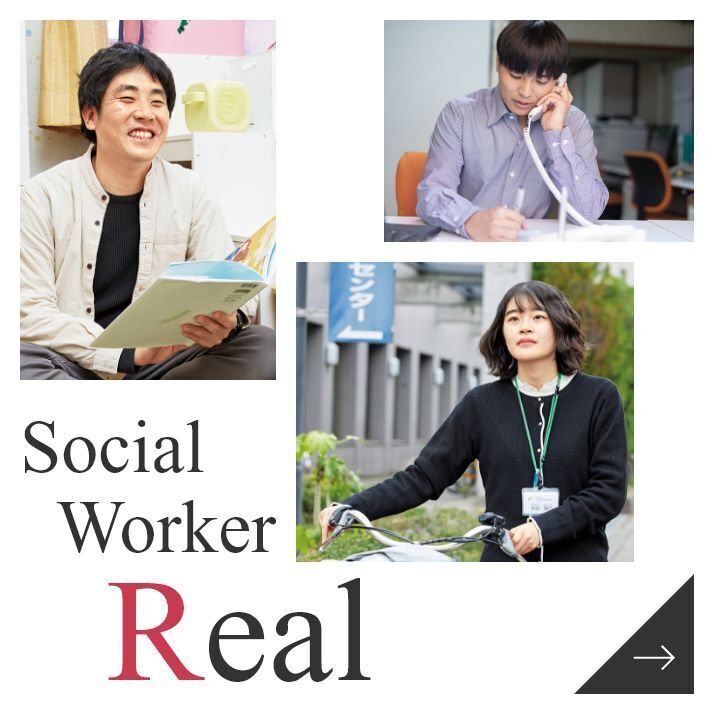09障がいの有無にかかわらず一人ひとりのニーズに
寄り添えるサービスを実現するには?

解に挑む研究者
大部 令絵准教授
社会福祉学部 福祉援助学科
- Profile
- 2007年筑波大学大学院修士課程教育研究科障害児教育専攻修了。修士(教育学)。2015年筑波大学大学院人間総合科学研究科障害科学専攻博士後期課程修了。博士(障害科学)。筑波大学教育開発国際協力研究センター非常勤研究員、埼玉県立大学保健医療福祉学部特任助教、日本女子大学人間社会学部社会福祉学科助教を経て、2022年に日本社会事業大学通信教育科専任講師に着任。2025年4月より現職。専門分野は障害者福祉、障害者心理。
近年、話題に上ることが多くなった「合理的配慮」。これは、障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」と意思表示されたときに、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で必要な調整や配慮を行うことを指します。誰もが平等にさまざまなサービスを受けられる社会を実現するには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。障害科学を専門とする大部令絵准教授の取り組みをご紹介します。
#障害者イメージ#バリアフリー接遇
SDGsアクション


海外調査から見えた、
文化的・社会的背景に基づく
障害啓発の大切さ
私の研究分野である障害科学は、障害を通じて「人間とは」という問いに答え続ける学問です。この魅力こそが、今日まで研究を続けてきた原動力だと言えます。
大学院時代には、インドネシアの自閉症児教育について現地教員にインタビューを行い、教育実態や教員が感じる課題を明らかにしました。印象的だったのは、保護者が障害を恥じてその存在を隠す、あるいは障害のある子どもを学校に通わせない、といったエピソードをいくつも耳にしたことです。障害者に対する固定的なイメージが、子どもたちの生活に深刻な影響を与えている実情があったのです。
次に、調査対象者をインドネシア国内の大学生に変えてみたところ、彼らにも障害者に対して固定的なイメージがあることがうかがえました。ただし、障害者と接した経験があるかどうか、あるいは調査対象者の性別によっても、抱くイメージは変化するという結果も得ました。

日本にもすでに同じような先行研究がありましたが、インドネシアの調査では独自の文化や社会の行動規範に左右されている面が見受けられます。したがって、日本の障害啓発運動をそのまま持ち込んでも同じような成果はあげられないかもしれない、というのが私の結論でした。
障害啓発運動を効果的なものとするためにはその国の文化的・社会的背景を含め、現地で暮らす人々の生活への理解を深める必要があります。この視点は、地域での持続的な活動を目指す支援にも共通する重要な要素であり、いまもなお大切にしています。
誰もが楽しく過ごせる
「バリアフリー接遇」を求めて
もう一つ、大きな研究テーマとしてかかげているのが「バリアフリー接遇」です。これは、いまあるサービスのなかで行われる特別な配慮を指します。街なかの設備をバリアフリーにする、新たなユニバーサルデザインの建物を建てる、障害者の固定イメージを変えようとする――。こういった取り組みとともに、一般的なサービスに含まれるバリアを取り除くこともまた重要であると考え、研究を進めてきました。
すでにあるバリアフリー接遇に関するガイドラインやマニュアルには、障害の種類に応じた典型的なニーズが書かれていますが、私はこれに違和感を覚えています。同じ障害や疾患だとしても、その程度や生活スキルには個人差があり、一人ひとりのニーズも当然異なります。したがって、求められるバリアフリー接遇の内容も、本来は簡単に障害種別でくくれるものではありません。

とはいえ、バリアフリー接遇にあまりなじみのない業界・企業においては、こうしたガイドラインの存在がよりどころとなるのは確かです。今後は、研究を通じて「個別性の高いものか」「受ける側が内容を自由に選択できるか」といった観点でサービスを分類し、さまざまなサービスに共通して求められるバリアフリー接遇の内容などを、明らかにしたいと考えています。その先には、より幅広いサービス分野で活用できる、バリアフリー接遇のガイドラインやマニュアルの作成につなげていけるのではという狙いがあります。
私の身近にも、特別なニーズのある人はたくさんいます。一緒にランチや買い物、旅行を楽しむこともよくあります。しかし、彼らが外出先でサービスを受けるには、自分のニーズを説明し、それに応えてもらえるかを交渉しなければなりません。交渉に失敗すれば別の行き先にする、あるいは外出そのものを諦める場合もあります。こうした手間を少しでも減らし、誰もが楽しさを分かち合えるよう、私の研究が役に立てばうれしいです。
問題の裏側に目を向けて
適切な「合意」と「配慮」について考える
最近では、生活のあらゆる場面で「合理的配慮」が求められるようになってきました。合理的配慮のポイントは、「対話」「調整」「合意」の3つです。たとえば「対話」には、合理的配慮を必要とする人が自分のニーズを相手に伝えることも含まれますが、なかにはコミュニケーションそのものに配慮を必要とする場合もあります。その点を意識せず合意にいたったとして、果たしてそれは適切なものと言えるでしょうか。こうした問題の裏側にある、「合意」の形と具体的な「配慮」の内容について、今後の研究で明らかにしていきたいです。
研究者は「究めた人」ではなく「究める行為をしつづける人」だと思っています。私の研究は、多くの方の協力のもとに成り立っています。厳しいご意見をいただくときもありますが、どれも私にとっては勉強になることばかりです。ソーシャルワークという人の幸せを追求する営みを研究していくにあたり、人とのかかわりの中で学びを得られるのは非常にありがたいことです。その気づきをまた次の研究に生かせれば、こんなにうれしいことはありません。


人の役に立ちたい、人を幸せにしたい、と考えるのはとても大切なことです。一方で、福祉を学び、福祉に従事するのもまた人です。福祉が、他者のためだけでなく自らの幸せにどのように結びつくのかという視点をもって学び、実践していく――。すなわち福祉を自分ごととしてとらえる姿勢こそ、モチベーション高くよりよい支援を目指すうえで欠かせないことだと思います。