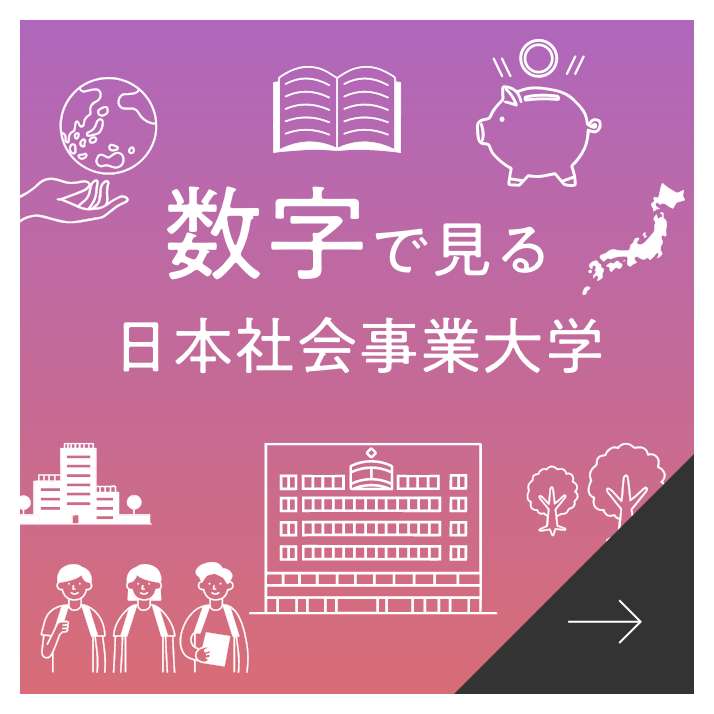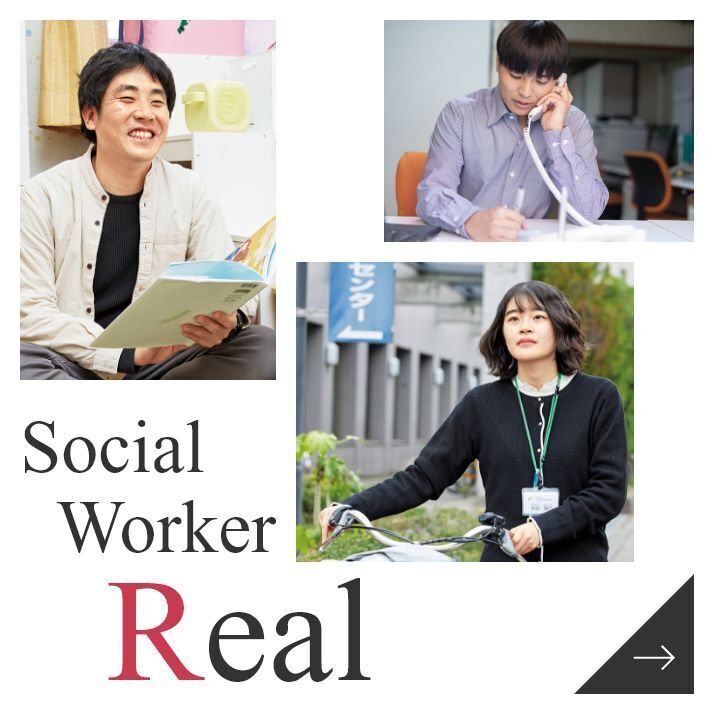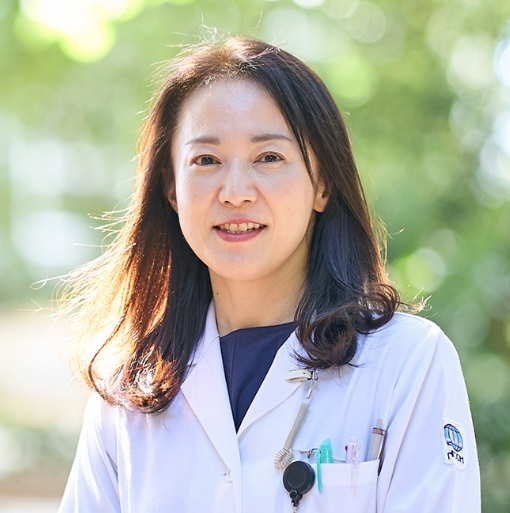時代の先を行く新たな試みを灯す
Chapter 01
ボーダーを取り除く
ご自身が代表をつとめる愛川舜寿会の事業内容についてお聞かせください。
僕は法人の2代目理事長で、2010年から経営にたずさわっています。1992年に父母が立ち上げた愛川舜寿会は、特別養護老人ホーム1施設で高齢者福祉に取り組んでいましたが、僕が2代目として関わるようになってから、少しずつ事業の多角化が進んできました。現在では高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉などの事業を展開しています。
すべての拠点に共通しているのは、地域の人が自由に行き来できるようにしていること。20世紀に建てられた精神科病院や介護施設などには高い壁が設けられていることも少なくありませんが、僕らの法人では、あえてそれをなくしています。地域からちゃんと利用者の暮らしが「見える」ようにする必要があると思ったんです。

なぜ、そのような施設をつくろうと考えたのでしょうか。
僕が専門職大学院に入学した3カ月後の2016年7月。隣町の「津久井やまゆり園」で相模原障害者施設殺傷事件が起きます。僕にとって決して忘れることのできない出来事でした。あまりに身近で、あまりに痛ましい事件に、これからの福祉事業のあり方を突きつけられたんです。
「人びとにとって障害者が身近な存在であったなら、この痛ましい事件は起こらなかったのではないか。二度とこのような事件が起こらないようにするためには、暮らしや多様な人びとの姿が地域の風景として自然に映るようにしていくこと。そのために模索を続けていくことが必要なのだと思います」
「"壁の中で守られる暮らし"が本当に人を守ることにつながるのか。むしろ、壁を壊し、地域とつながることからしか希望は生まれないんじゃないか」
そう考えて、施設の壁を物理的に壊し、誰もが庭に自由にアクセスできる空間へと変えました。事件の直後にこの方向へ舵を切ったことに、意義があったと感じています。
以来、僕らの法人では「見える」ことを大切にし、だれもが福祉施設に立ち寄りやすくなるような工夫を随所に散りばめています。コインランドリーや洗濯代行、駄菓子屋、コロッケスタンド、コモンスペース、利用者と目線を合わせて話せる縁側......。どれも地域の方々が日常の延長で立ち寄れる仕掛けです。
2階での学習支援や公文に通う子どものお迎えついでに駄菓子を買う親子、あるいは、洗濯をしに来た人が揚げたてのコロッケを手に取る姿など、地域の人びとの日常がここにはあります。
そうした日常の動線上で、利用者や働く障害者の暮らしが自然に目に入る――。 小さな接点の積み重ねが、障害のある方々への認識を少しずつ変えていくのだと思っています。




社会をひらく覚悟を灯す Chapter 02
「福祉とは社会事業」 その気づきが覚悟の後押しに
「福祉とは社会事業」 その気づきが覚悟の後押しに
専門職大学院時代は、どのように過ごされましたか。
実は法人を継ぐ前は、ファッション業界にいたんです。当然最初は福祉について何もわからず、業界や組織の文化の違いにも戸惑う日々でした。
そこで福祉に関する基礎知識やマネジメントについてきちんと学ぶべきだと思い、日本社会事業大学の専門職大学院に入りました。「福祉マネジメント」と名のつく研究科は、当時めずらしかったと思います。法人の代表、組織をマネジメントする立場として必要な知識を得るには、といくつかの候補の中から決めました。
専門職大学院はさまざまな職種のプロフェッショナルがつどう場所。学生のなかには児童相談所や教育機関、障害者支援など、僕と違うフィールドで活躍されている方も多かった。彼らとともに、社会課題と真剣に向き合うなかで、カルチャーショックを受けたこともあります。
たとえば、高齢者介護は誰もがいずれ直面する課題の一つです。けれども児童虐待は、家庭や関係者の重層的な課題が絡み合って生じる、より深刻な問題でした。身体的な暴力や性的虐待、ネグレクト......と、本当に重くて苦しいテーマばかり。議論のたびに胸がつぶれる思いもしました。それでも、そこに目を背けず向き合うことこそが福祉の現場に立つ者の責任。その重さを引き受けて学んだ時間は、今の自分にとって大きな糧になっています。
愛川舜寿会はいまでこそ多角的に事業を展開していますが、僕が参画した当初は高齢者福祉の事業だけでした。だから児童や障害に関する課題に正面から向きあったのは、ここでの学びが初めて。正直、本当に不勉強だったと感じますし、改めて福祉の世界の深さと広さを嫌ってほど思い知らされました。
もう一つ、社大の専門職大学院に入学を決めた理由として、大学名の"社会事業"という枠組みを表す言葉に魅力を感じた、というのも大きかったんです。異なる分野や多様な専門職との出会いを通じて、分野横断的な"社会事業"を目指そうという思いが強まりました。その過程で、社会を前に進める一員としての覚悟も芽生えたんです。
大学院と聞くと「専門性を深める場」という印象が強いかもしれませんが、専門職大学院はそれだけにとどまりません。僕が経験させてもらったように、むしろ、まちづくりの視点を持って、福祉と地域をつなぐ接点をつくりたい人にこそ意味のある場だと思います。たとえば、福祉の専門性や組織内をパラダイムシフトさせたい人だけでなく、多様な素材を織り合わせて、強くしたり、しなやかにしたりすることで社会変革を生み出す事業をしたい人や、法人の後継者などが学ぶにふさわしい場ではないでしょうか。これから専門職大学院に進む人には、ぜひその実感をつかんでほしいと思います。

互いに支えあう社会へと願いを灯す Chapter 03
当たり前に溶け合えるように
今後の展望や、目指す福祉のリーダー像についてお聞かせください。
これからも「見える」ことを大切にした法人の運営に取り組んでいきたいと考えています。
福祉のリーダー像を考えるとき、僕にとって大きなヒントを与えてくれるのは志村けんさんです(笑)。
彼が演じていた「変なおじさん」って、幅広い世代に親しまれたキャラクターでしたよね。志村けんさんが育った時代や地域には、個性的でちょっとクセのある大人や凸凹な人がいて、でも、みんなが自然に共存していた。福祉の視点から見れば、その中には知的に障害のある人もいたかもしれません。昔はそうした多様な人が当たり前に近所にいて、地域と溶け合っていたじゃないか。――そんな思いが、彼の芸風に映し出されていたように思うんです。
志村さんの芸風は間違いなくそういう世相を反映していたし、でもそこには「変な=まわりとはちょっと違う」人たちへの"愛情とまなざし"が確かにあった。だから社会は笑い合えたんだと思うんです。僕らも事業を通して、このまちにとってそういう存在でありたいと願っています。
そして経営者としては、福祉を起点にした社会事業のあり方を問い続け、地域のあらゆる世代が自然に交わり支え合える文化をつくりたい。地域の子どもたちが大人になったとき、「僕らのまちにはいろんな人が一緒にいた」という体験を次の世代に引き継げるように、20年後を見据えた実践を続けていきたいと考えています。


Message
「福祉の仕事はこういうものだ」という決めつけがあるとすれば、それをつくってきたのは私たち自身かもしれません。だからこそ、ちょっと違う見え方や関わり方を広げていきたい。何かと不安に包まれやすい時代だからこそ、人と人のあいだに寛容さを取り戻すことが大事だと思います。志村けんさんの言葉を借りれば――「だいじょうぶだぁ」ってこと。この一言そのものがケアであり、社会を静かに変えていくきっかけになると思うのです。