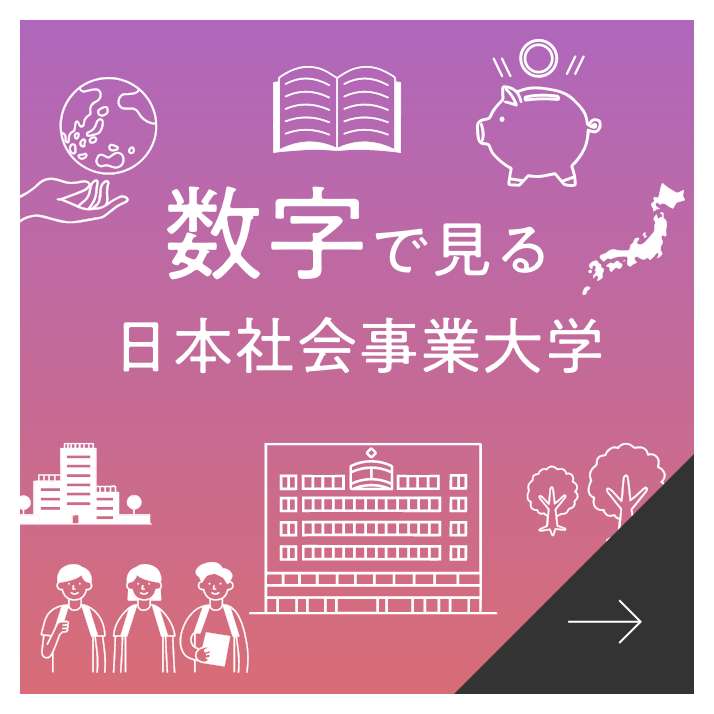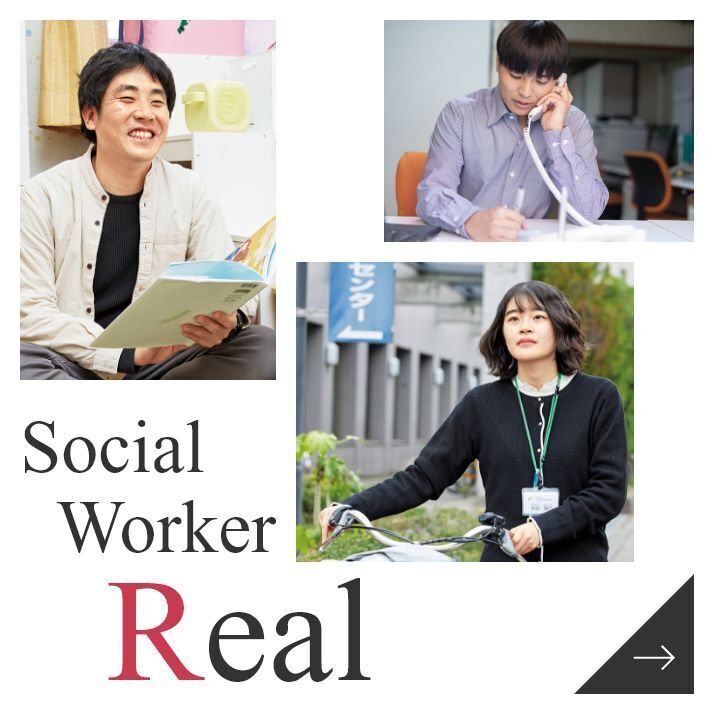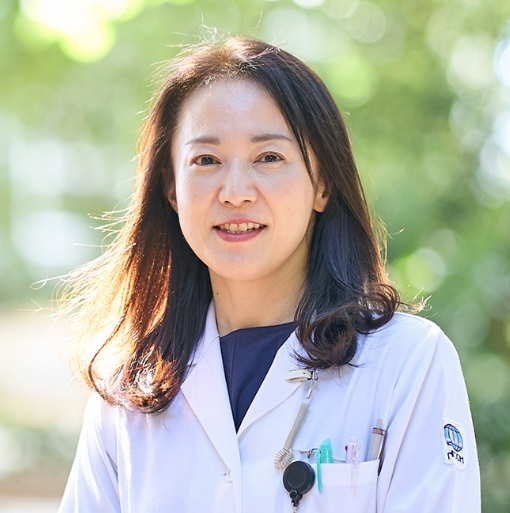学ぶ意味への気づきを灯す
Chapter 01
確かな知識で課題に対応する
現在の道に進まれたきっかけを教えてください。
日本社会事業大学卒業後、しばらくは医療ソーシャルワーカーとして病院で働いていました。当時、実践の課題として感じていたのは、どうすればうまく他職種と協働できるか、ということです。患者さんが退院後も安心して生活できるようにするには、在宅医療の領域や地域社会との連携が重要だからです。
ちょうど福祉の専門家間では、「理論に裏打ちされた実践」の大切さが言われ始めた頃でした。しかし、私が行っている他職種との連携は、経験だけを頼りにしている。果たしてそれが患者さんのためになるのだろうかと、自問するようになりました。
そこで、多職種連携や地域福祉などの理論をしっかり学ぼうと、働きながら日本社会事業大学の社会福祉学研究科に進んだのです。
大学院での学びで気づいたのは、教育、研究、実践はすべてつながっているということ。実践の先には学びが、学びの先には研究があります。そして、研究の成果はやがて実践に還元されます。教育者・研究者になっても実践現場に貢献できると考え、最終的に大学教員の道を選びました。
以来、多くの学生を福祉現場に送り出し、実践に役立つようにと研究活動に励んできました。
主に専門職大学院生の教育・研究指導を担当されていると伺っています。
はい。実践で使うようなソーシャルワーク方法論や理論について教えています。具体的には支援方法論や、実践現場を動かしていくための役割・体制づくりにかかわるスーパービジョン、多職種連携でチームを動かすインタープロフェッショナルワークなどです。
教育において大切にしている点は、主に二つ。
一つは、学生たちが自然に膝を突き合わせて話せる場づくりですね。
たとえば一人が自分の職場の課題を口にすると、周りから次々とそれぞれのキャリアの視点に立ったアドバイスをするような雰囲気があります。
学生のなかには福祉職の人もいれば、医療など他分野の人もいます。いろいろな課題をもっていて、意見もさまざまです。一つの問題について、幅広い分野の専門職が「ああでもない」「こうでもない」と多角的な検討を行っています。これは、専門職大学院のいいところだと思います。
また、教育、研究、実践のサイクルも変わらずに大切にしています。

学び舎への変わらぬ思いを灯す Chapter 02
変わらない温かさこそ 私がここにいる理由
大学生、大学院生、教員として、ずっと日本社会事業大学と深いかかわりをもっていらっしゃいますが、どういう点が魅力なのでしょうか。
大学や教員、学生からにじみ出ていた「本気で福祉をやるぞ」という思いの熱さです。
特に私が大学生だったころは、まだいまほど「多様性」という言葉が浸透しておらず、社会的弱者の立場は本当に厳しいものでした。そうした方々のためにどれだけ真剣に行動できるのか、という覚悟が問われていたと思います。もちろん、いまの社大生にも、福祉への思いの熱さは受け継がれている気がしますね。
また、先生方との距離感の近さも魅力に感じていました。
学生が開く勉強会へのご出席をお願いすると、こころよく引き受けてくださる先生ばかりでした。逆に卒業後に先生方のゼミにお邪魔したこともありました。
ちなみに私に社大の大学院への進学を進めてくださったのも、恩師です。
木戸先生にとって、日本社会事業大学とはどのような場所でしょうか。
居心地のいい場所です。私のいた原宿キャンパスは1学年100人程度といまのキャンパスの半分ほどの人数で、よりアットホームな雰囲気がありました。勉強だけでなく、アルバイトやサークル活動、友人や先生方との交流から、福祉職としてはもちろん、人間的にも成長できたんじゃないかなと。
社大は温かい雰囲気で、私が自然にいられる場所。だから、卒業してもおのずと足が向いたし、教育者・研究者としてもここにいるのかと思います。

未来をひらく後輩たちへの願いを灯す Chapter 03
社大の通信教育科には、社会福祉士(一般、短期)、精神保健福祉士(短期)、社会福祉主事の養成課程があると伺っています。他機関の通信教育と比較してどのような魅力があるのでしょうか。
やはり「リアルなキャンパスで学べる機会もある」という点が大きいと思います。受講生の皆さんには、普段おのおの課題に取り組んでもらっていますが、スクーリングでキャンパスに来る機会も設けています。
そうすることで大学や教員とのかかわりができ、より深い学びや、将来のキャリアを描く手がかり、人脈などが得られるのではと考えています。
通信教育と聞くと一人でコツコツ学ぶイメージがあると思いますが、社大の通信教育科では、大学のキャンパスで学ぶメリットをしっかり感じていただけるかと思います。
学生の皆さんに対して、どのようなことを望まれますか。また、ご自身の今後の展望も教えてください。
学生には、ずっと学び続けてほしいですね。それも「働きながら」学んでもらえるとうれしいです。
実践現場では常に新しい課題が生まれています。
どんな課題があるのかアンテナを張り、理論に裏打ちされた解決方法を提案できるようになってほしいですね。
私自身の目標としては、日本社会事業大学の校歌にある「社会の福祉誰(た)が任ぞ」を我が任ぞとして実践できる人でありたいです。自分も周りも尊重する、という意味で、これこそまさにソーシャルワーカーに必要な資質だと感じます。もちろん、教育者として今後もそういう人たちを育てていきたいという気持ちもあります。

Message
社会は常に目まぐるしく変わっていくもの。時代が進むにつれ、次々と新たな社会課題が生まれます。福祉職を目指すみなさんとともにこれらを解決し、新たな福祉実践にチャレンジしていきたいですね。日本社会事業大学は専門職大学院や通信教育科を設け、働きながら学びを深めて実践に還元したい、という方に広く門戸をひらいています。ぜひ、多くの方に興味を持っていただけたらと思います。