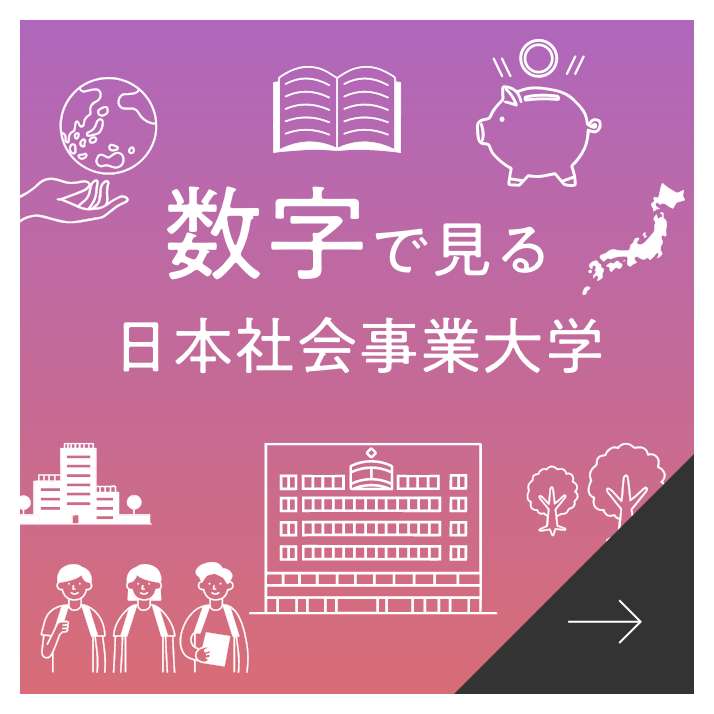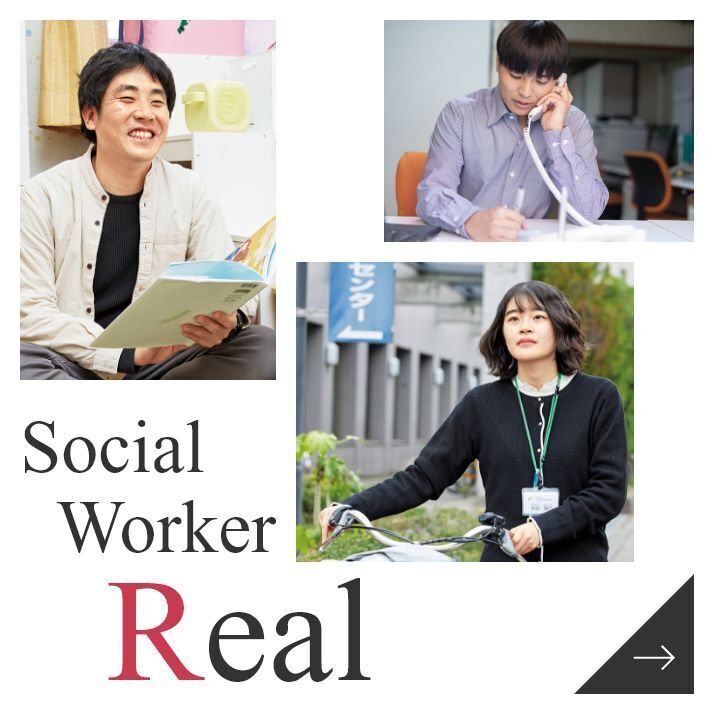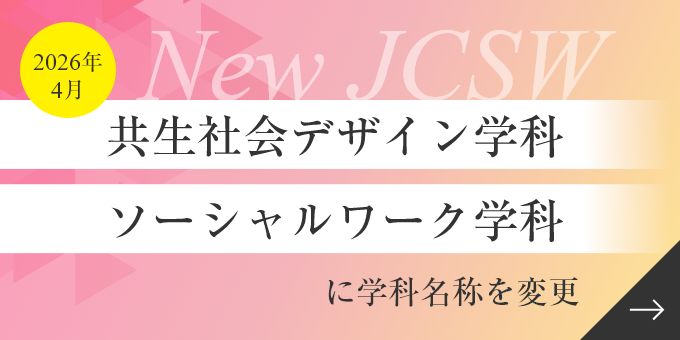地域福祉コース
コースの特長
個別支援と地域支援の統合による地域福祉の推進方策を学ぶ。
地域生活を支えるための個別支援だけでなく、暮らしている環境に対する地域支援の具体的方策について学びを深めます。講義だけでなく、地域福祉の実践現場でのフィールドワークも豊富です。
多岐にわたる分野と連携し、あらゆる生活ニーズに向き合う。
保健・医療・教育・司法・労働など多分野との横断的連携が不可欠な地域福祉の現場。幅広い領域の学習を通して、制度の狭間のニーズにも向き合い、地域福祉を推進するリーダーを育成します。
専門性を身につける「履修モデル」
地域福祉計画履修モデル 卒業単位(127)/履修科目(22)
自治体の福祉計画をもとに、高齢者や障がいのある方が地域で自立した生活を送るための施策を学びます。サービス提供のシステム、医療などの他分野との連携、住民参加による地域福祉計画づくりについても学びます。
介護保険制度論(2)、子どものケースマネジメント(2)、社会福祉調査・計画演習I(4)、社会福祉調査法II(2)、住環境支援法(2)、生涯学習論I(2)、精神保健福祉の原理I(2)、地域ケアシステム論(2)、福祉と経営(経済)(2)、福祉と計画(行政計画)「福祉計画の世界」(2)、福祉と政策(理論)(2)、福祉と政策(歴史)(2)、リハビリテーション論(2)
※( )は単位数
コミュニティ・ソーシャルワーク履修モデル 卒業単位(127)/履修科目(22)
支援を必要とする人のニーズを把握し、地域の福祉サービス・制度と結びつけていく福祉計画の具体的な手法を学びます。保健・医療機関との連携、新サービス開発、市民の福祉意識の向上についても取り上げます。
介護保険制度論(2)、ケアマネジメント論(2)、健康福祉増進論(2)、高齢者社会教育論(社会教育課題研究II)(2)、子どものケースマネジメント(2)、コミュニティ・ソーシャルワーク論(2)、住環境支援法(2)、生涯学習論II(2)、障害者社会教育論(社会教育課題研究I)(2)、精神保健福祉の原理I(2)、地域ケアシステム論(2)、福祉機器活用法(2)、福祉と計画(行政計画)「福祉計画の世界」(2)、福祉と法(家族法)(2)、福祉と法(民法)(2)、リハビリテーション論(2)、レクリエーションワーク(2)
※( )は単位数
ゼミの紹介(2025年度)
| 教員名 | ゼミのテーマ |
|---|---|
| ヴィラーグ ヴィクトル 学科長/准教授 |
文化や性などの多様性とソーシャルワーク、国際社会福祉 |
| 梶原 洋生 教授 |
社会福祉と法、司法福祉 |
| 田村 真広 教授 |
教育福祉と福祉教育;「今を生きぬく学び」と「学び直し」 |
| 菱沼 幹男 教授 |
地域生活支援のあり方とコミュニティソーシャルワークに関する研究 |
| 倉持 香苗 准教授 |
地域福祉の推進に関する研究~様々な領域と地域福祉~ |
| デバコタ ジバナト 講師 |
グローバル及びローカルな視点からの社会問題とその解決法(ジェンダー・移民・貧困・教育) |
卒業研究題目例
- 家出をせざるを得ない若者たちへの社会的支援 ―支援団体へのインタビュー調査を通じて―
- マスメディアにおける利他性 ―孤独と孤立を音声で支える―
- 日本におけるホームレス支援の在り方 ~地域生活へ向けて~
- 被災者の孤立を防ぐために必要な支援について
学生インタビュー/学生・ゼミ教員 対談
学生インタビュー/学生・ゼミ教員 対談を下記ぺージに掲載しています。ぜひご一読ください。