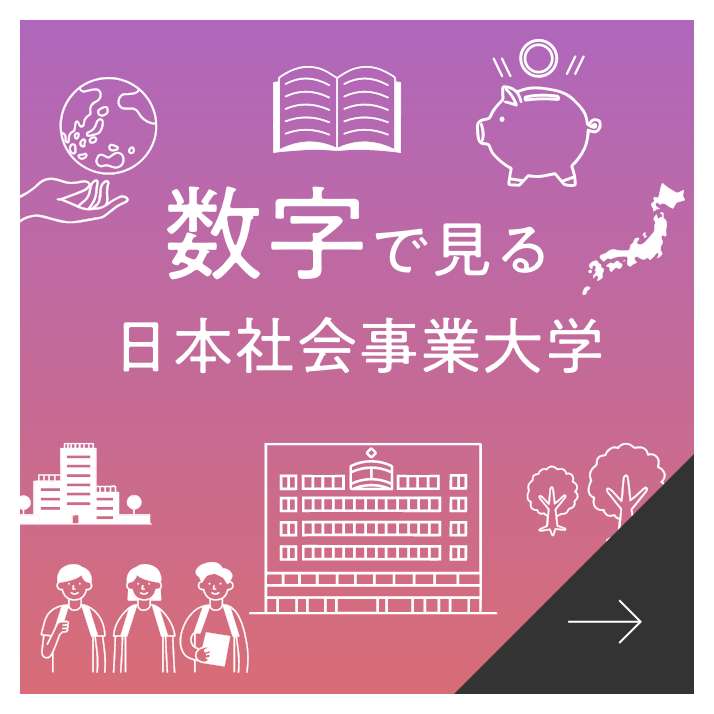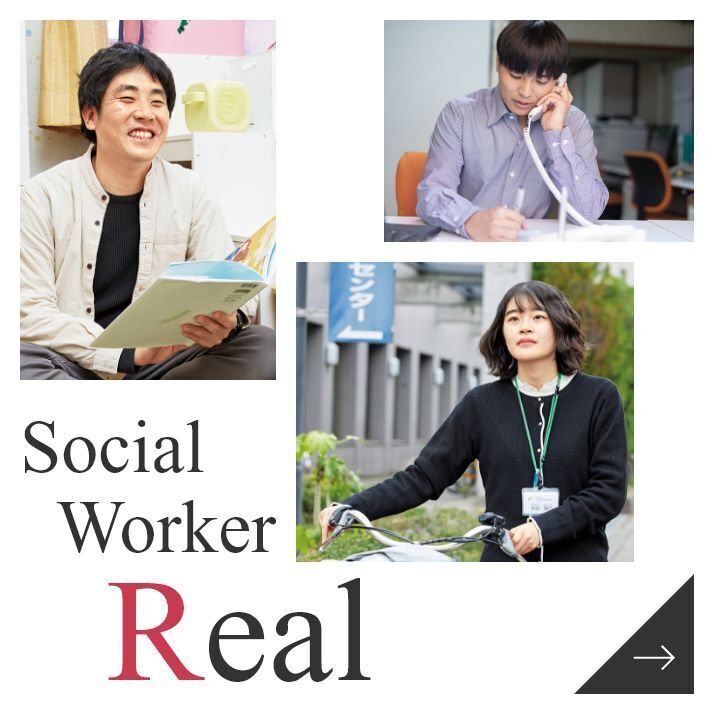福祉経営コース
コースの特長
制度・政策や福祉経営の面から具体的な改善方策を立案する。
社会福祉に関わる制度の成り立ちや歴史を学ぶとともに、福祉サービスを必要とする人々に生じている問題について把握します。その解決に向けて、法・経営・計画・政策の面から具体的な改善方策を考えます。
重要視されているテーマと向き合い時代のニーズに応える力を育む。
福祉計画の策定や施設のより良い経営、サービス利用者への情報提供、利用援助など、重要視されているテーマを学習。利用者の現状を分析し、時代のニーズに応えるシステムを構築・運営する力を育みます。
専門性を身につける「履修モデル」
福祉経営履修モデル 卒業単位(127)/履修科目(22)
福祉サービスを必要とする人々の問題を把握し、その解決に必要な制度・政策や福祉経営について、実施上のシステムなどを含めて学びます。福祉サービスが措置から契約・利用制度へと転換するなか、利用者への情報提供などの重要なテ-マも学びます。
福祉と経営(経済)(2)、福祉と経営(施設)(2)、福祉と計画(行政計画)「福祉計画の世界」(2)、福祉と政策(国際)(2)、福祉と政策(理論)(2)、福祉と政策(歴史)(2)、福祉と法(家族法)(2)、福祉と法(民法)(2)、福祉計画学科開講科目の中から適宜履修(6)
※( )は単位数
ゼミの紹介(2025年度)
| 教員名 | テーマ |
|---|---|
| 入部 寛 教授 |
社会保障の制度・政策と現場の実践の相互作用を意識した研究 |
| 贄川 信幸 教授 |
福祉課題解決に向けたプログラム開発・改善と評価、精神保健福祉 |
|
村田 文世 |
社会福祉を担う多様な供給主体(組織)と公私協働 |
|
上村 勇夫 |
多様な社会参加を目指した支援・特に、労働に関わるソーシャルワーク |
| 佐々木 貴雄 准教授 |
社会の変化に対応した社会保障 |
卒業研究題目例
- 市民の生活保護制度に対する認識とは -生活保護制度の不正受給認識に焦点をあてて-
- 教育支援センター(適応指導教室)における不登校児童生徒の集団適応能力の向上に向けて
- ヤングケアラーの支援と課題
- SNSの利用と幸福度の関係について ―SNSと成長する若者に着目して―
学生インタビュー/学生・ゼミ教員 対談
学生インタビュー/学生・ゼミ教員 対談を下記ぺージに掲載しています。ぜひご一読ください。